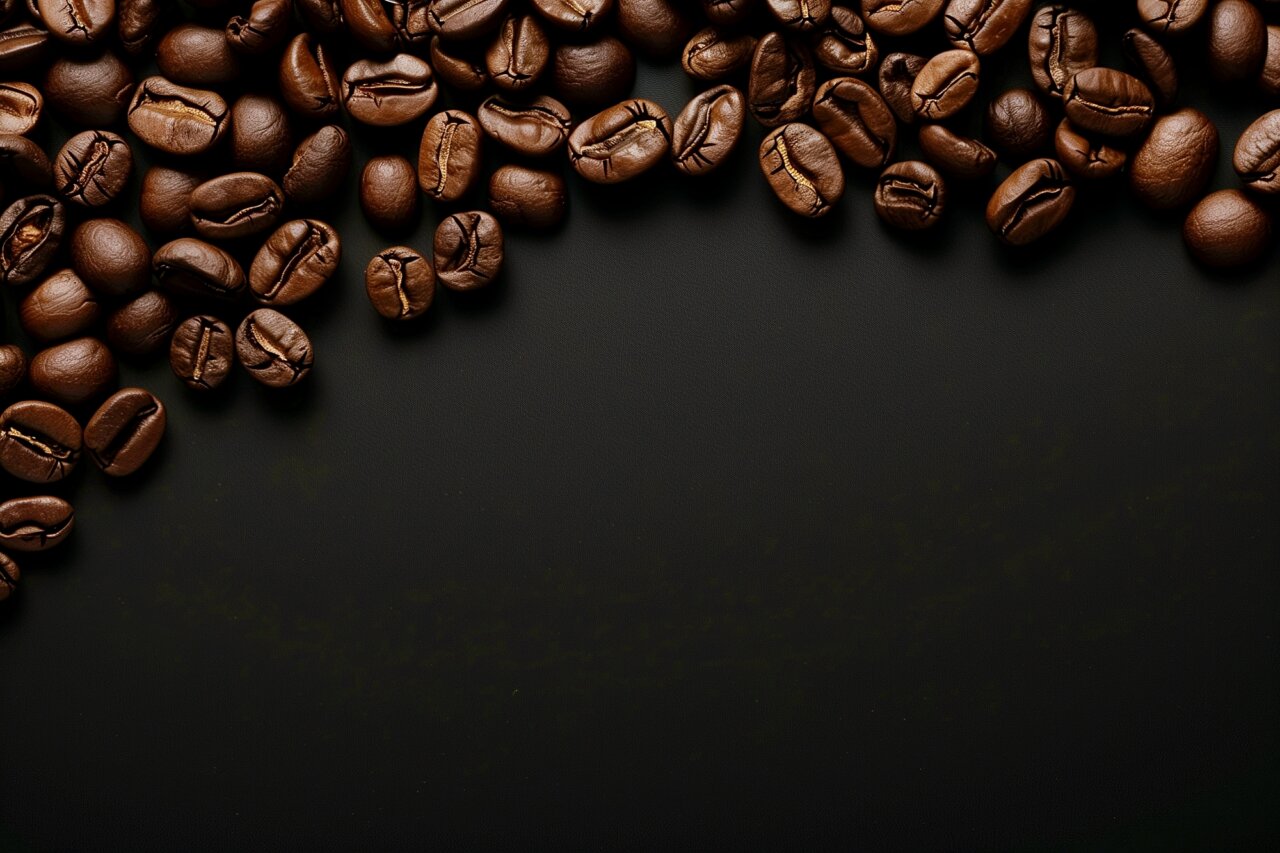夕方の倦怠感?朝の動きづらさ?あなたの疲れはどのタイプ?

こんにちは、Drip & Dose Journalへようこそ!
「休んでも疲れが取れない…」「朝から体が重く、動き出すのがつらい」「夕方になると倦怠感が増す」
慢性的な疲労は、多くの人が悩む症状のひとつですが、原因やタイプによって改善法が異なります。東洋医学では、疲労の原因を「気虚」「気血両虚」「気滞」の3つに分類し、それぞれに適した漢方処方や養生法を提案しています。
本記事では、疲労の種類ごとの原因と漢方的なアプローチで根本改善を目指します。
疲労とは
疲労は多くの人が日常的に感じる症状のひとつであり、特に現代の生活環境では慢性的な疲労が問題視されています。 統計データによると、日本人の約60%が「慢性的な疲労」を自覚していると報告されており、特に30代〜50代の働く世代での疲労感が強くなっています。
疲労は単なる「疲れ」ではなく、体内のエネルギー不足や巡りの乱れが影響していることが多いです。
疲労の主な症状
疲労は「ただの疲れ」ではなく、回復しにくくなる状態を指します。主な症状は以下のようになります。
✅ 倦怠感(常に体が重い) → 約55%以上の人が経験
✅ 集中力の低下 → 約50%の人が「仕事や学習に影響がある」と回答
✅ 朝起きても疲れが抜けない → 約40%の疲労持ちが経験
✅ 夕方になると極度の疲れを感じる → 約45%が午後〜夕方の疲労を訴える
✅ 睡眠の質が悪く、寝てもすっきりしない → 約35%の疲労患者にみられる
特に、朝の目覚めが悪い・夜になっても疲れが取れないといった症状が続く場合、慢性的な疲労が進行している可能性があります。
疲労を引き起こす生活背景
疲労は、日々の生活習慣によって悪化しやすく、特に以下の要因が関係しています。
1. 睡眠不足
✅ 日本人の平均睡眠時間は6時間台(世界的に短い)
✅ 睡眠が6時間未満の人は疲労を感じる率が約70%
✅ 寝ても疲れが取れないと答えた人は約40%
睡眠不足が続くと、自律神経が乱れ、体の回復が遅れるため、翌日のパフォーマンスも低下します。
2. 運動不足
✅ 運動習慣がない人の約60%が慢性的な疲労を抱えている
✅ 週に1回以上軽い運動をする人は疲労感が約30%減少
✅ デスクワーク中心の人は約50%が「体のだるさが抜けない」と回答
血流が悪くなることで、筋肉の疲れが蓄積しやすくなり、疲労が抜けにくい状態になります。
3. 栄養不足・食生活の乱れ
✅ 栄養バランスが偏っている人の約45%が疲労を感じやすい
✅ 朝食を抜く人は疲れやすい傾向があり、約30%が「午前中から疲れる」と回答
✅ 鉄分不足・ビタミンB群不足があると、約40%が倦怠感を自覚
食事から得られるエネルギーが不足すると、身体が正常に機能せず、疲れを回復しづらくなります。
4. ストレス
✅ 強いストレスを感じている人の約55%が慢性的な疲労を抱えている
✅ 仕事や人間関係のストレスが疲労の原因と答えた人は約50%
✅ ストレスが原因で睡眠が浅くなる割合は約40%
ストレスによって交感神経が過度に働くと、体の回復力が低下し、疲労が蓄積しやすくなります。
疲労の予防と生活改善
疲労を改善するためには、以下のような習慣を取り入れることが重要です。
✅ 睡眠時間をしっかり確保し、生活リズムを整える
✅ 適度に運動し、血流を良くする
✅ バランスの良い食事を意識し、必要な栄養を摂る
✅ ストレスを軽減し、リラックスする時間を作る
✅ スマホ・PCの使用時間を見直し、目の疲れを減らす
東洋医学では疲労のタイプ別に漢方処方を活用することで、根本的な改善が可能になります。
気虚による疲労—夕方になるとエネルギー不足に
特徴
✅ 午前中は比較的元気だが、夕方になると疲れやすい
✅ 食事をしても回復しにくい
✅ 気持ちが落ち込みやすく、集中力が低下する
症状の特徴
体内の「気(エネルギー)」が不足している状態。特に夕方になると倦怠感が強くなる傾向があります。
こまめに休みをとり、夜はしっかりと睡眠をとるように心がけましょう。
漢方処方
☑ 補中益気湯(ほちゅうえっきとう) → 気を補い、持久力を高める
※元気が出る升麻(しょうま)や柴胡(さいこ)が配合されている。
☑ 六君子湯(りっくんしとう) → 胃腸の働きを整え、気を生み出し消化吸収をよくする
このタイプの疲労は、「気を補いながら、エネルギーを安定させる」ことがポイントになります。
気血両虚による疲労—気の不足が進み、血も足りなくなる
特徴
✅ 気だけでなく、血の不足も感じる(顔色が悪い)
✅ 寝汗が出るようになり、夜の疲れが翌日まで続く
✅ 冷えを感じやすく、体力の回復が遅い
症状の特徴
気虚の人が、夜も頑張って仕事をしたり、目を使いすぎると血虚になりやすくなります。睡眠をとっても疲れが回復しない、寝汗をかくといった状態になると、かなり症状が悪化していると考えられます。気の不足が進行すると、血も不足しやすくなり、身体全体の栄養が足りなくなることで、倦怠感が強くなります。
漢方処方
☑ 十全大補湯(じゅうぜんたいほとう) → 気と血を補い、慢性的な疲れを改善
※自分の気血の容量を超えた生活をしている可能性があるので、生活を見直すことも大切。
このタイプの疲労は、「気と血を同時に補いながら、根本から改善する」ことが必要になります。
気滞による疲労—朝の動き出しが特につらい
特徴
✅ 朝が一番つらく、午前中は体が重い
✅ ストレスを感じると、さらに疲れやすくなる
✅ 眠りが浅く、質の低い睡眠が続いている
症状の特徴
気が停滞していることで、朝の体の巡りが悪くなり、起きたときに極度の倦怠感を感じることが特徴。
朝起きて、動き出すときが一番つらく、いったん仕事をはじめて気が回り始めると楽しくなってくるのが気滞タイプの特徴です。
漢方処方
☑ 四逆散(しぎゃくさん) → 気の流れを改善し、ストレスによる疲労を緩和
このタイプの疲労は、「気の巡りを改善しながら、自律神経を整えることが重要」になります。
養生・セルフケアのポイント
1. 過ごし方
✅ 適度な運動で血流を改善(軽いウォーキングやストレッチ)
✅ 長時間のデスクワークは休憩を挟む(1時間ごとに軽く動く)
✅ ストレス管理を意識し、リラックスする時間を確保
2. 食べ物
✅ 気を補う食材(玄米、山芋、黒糖)は気虚タイプ向け
✅ 血を補う食材(ナツメ、レバー、ほうれん草)は気血両虚タイプ向け
✅ 巡りを良くする食材(シソ、陳皮、生姜)は気滞タイプ向け
+α:お酢や梅干しといった酸っぱいものは、筋肉の緊張をとる効果があるので、疲れたときに摂ると体の緊張が和らぎ、よく眠れるかもしれません。
次回テーマ:肩こりの原因と漢方処方
次回のDrip & Dose Journalでは、「肩こり—東洋医学が示すタイプ別の改善法」 をテーマにお届けします。
✅ 「慢性的な肩こりはなぜ起こる?」その原因と体質の関係
✅ タイプ別の漢方処方(気滞・血虚・水毒による肩こり)
✅ セルフケアと養生法—肩こりを根本から改善する方法
あなたの肩こりはどのタイプ?東洋医学の視点で根本からの改善を目指しましょう!次回もお楽しみに。

【キーワード】
- 「疲労 漢方」
- 「気虚 疲れやすい 改善」
- 「十全大補湯 慢性疲労」
- 「朝つらい 疲労 気滞」
- 「漢方で疲労回復」