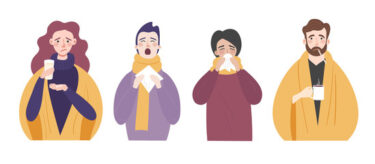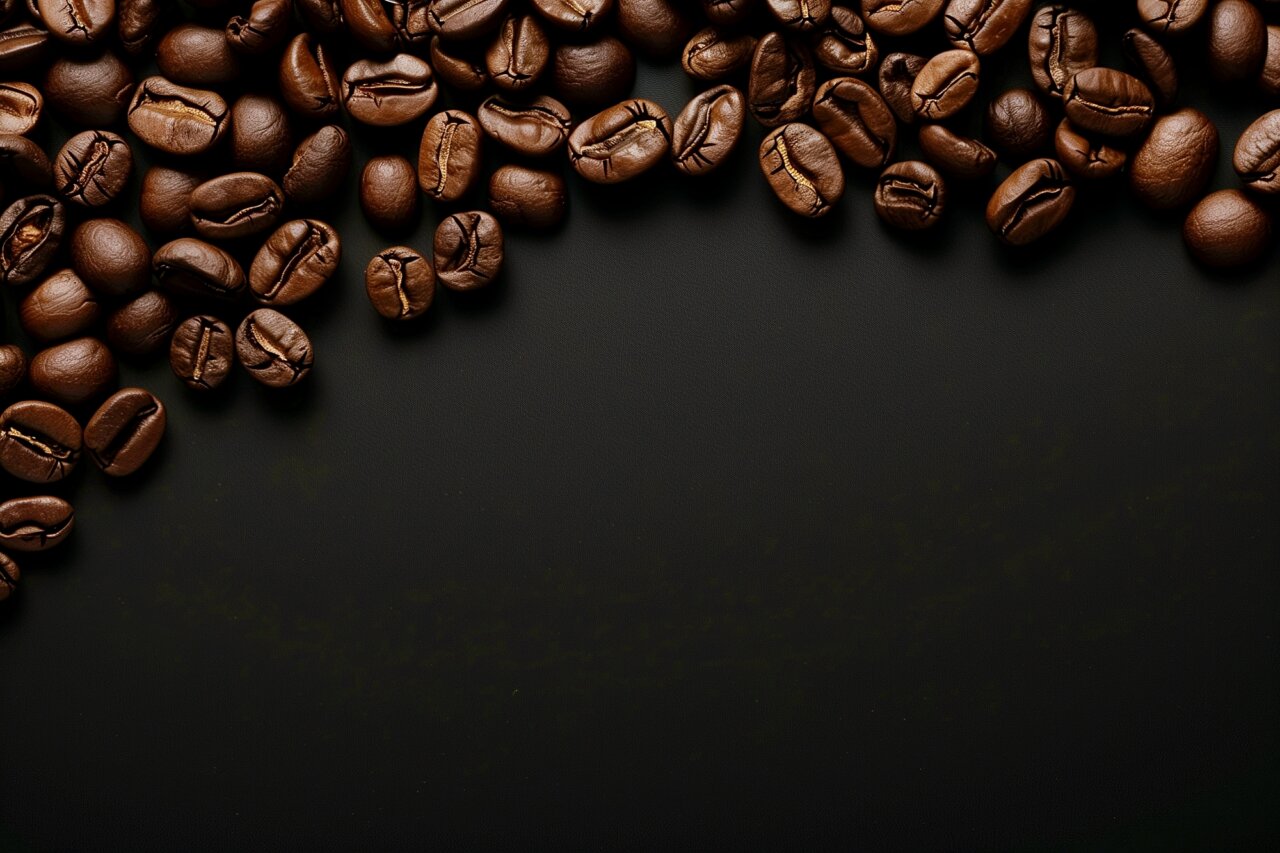冷え性の原因はひとつじゃない?タイプ別の対策で温かい体へ

こんにちは、Drip & Dose Journalへようこそ!「手足が冷えてつらい」「寒さを感じやすく、冬は耐えられない」「冷えが原因で不調が起こりやすい」冷え性は、多くの人が悩む症状のひとつですが、原因やタイプによって改善法が異なります。東洋医学では、冷え性を「陽虚」「血虚」「気滞」「水毒」の4タイプに分類し、それぞれに適した漢方処方や養生法を提案しています。本記事では、冷え性の基本からタイプ別の改善法、漢方の処方まで詳しく解説します。
冷え性の症状と生活背景
冷え性は、多くの人が抱える体調の悩みのひとつです。特に女性の約7割が冷えを感じるというデータもあり、男性よりも冷え性の割合が高い傾向があります。これは、筋肉量やホルモンの違い、血流の調整機能が関係しているためです。
冷え性の主な症状
冷え性は単に寒さを感じるだけではなく、以下のような症状を伴うことが多いです。
✅ 末端の冷え(手足の先が冷たくなる) → 約60%以上の冷え性の人が経験
✅ 全身の冷え(布団に入っても温まらない) → 約40%の人が該当
✅ 寒さによる肩こり・頭痛 → 約35%の人が冷えと関連して悩んでいる
✅ 胃腸の不調(冷えによる消化機能の低下) → 約25%の冷え性の人にみられる
特に、手足の冷えは最も多くの人が訴える症状であり、「手が冷たくて仕事や家事がつらい」「足先が冷えて寝付きが悪い」といった悩みが多く聞かれます。
冷え性になりやすい生活背景
冷え性は、生活習慣によって引き起こされることが多く、特に以下の要因が関係しています。
1. 食生活の乱れ
温かい食事を摂らない人は冷えを感じやすいという調査結果があります。特に、以下のような食生活が冷え性につながります。
✅ 食事のバランスが悪い(栄養不足) → 50%以上の冷え性の人が経験
✅ 冷たい飲み物・食べ物を頻繁に摂る → 冷え性の約45%に見られる
✅ 食事の回数が少ない、朝食を抜く → 約30%の人が該当
食事は体を温める重要な要素であり、特に朝食を抜くとエネルギー不足による冷えが起こりやすくなります。
2. 運動不足
運動不足は血流の低下を招き、冷え性を悪化させます。特に、運動習慣がない人の約60%が冷えを感じやすいという統計データがあります。
✅ 座りっぱなしの生活(デスクワーク中心) → 約55%の冷え性の人が該当
✅ 歩く習慣が少ない(1日5,000歩未満) → 約40%の人が冷えを感じる
✅ 筋肉量が少ない(特に女性) → 冷え性の約70%が関連
筋肉は熱を生み出す役割を持つため、筋肉量が少ないと冷えやすくなるという傾向があります。女性に冷え性が多いのは、筋肉量が男性より少ないことも影響しています。
3. ストレスや自律神経の乱れ
ストレスや緊張が続くと、交感神経が過剰に働き、血流が悪くなることで冷えが起こりやすくなります。
✅ ストレスが多い人の約50%が冷えを感じる
✅ 緊張しやすい性格の人は手足の冷えが起こりやすい(約40%)
✅ 睡眠不足が続くと冷えが悪化(約35%)
気滞による冷え性は、このようなストレス関連の要因が大きく関係しています。リラックスできる時間を増やすことが冷え性対策として重要になります。
4. 環境の影響
✅ エアコンの冷房を強く使う → 50%以上の冷え性の人が経験
✅ 薄着の習慣がある → 40%の人が冷えを感じやすい
✅ デスクワークで足元が冷えやすい → 30%の人が該当
職場や生活環境の影響も冷え性の原因になります。エアコンの冷風が直接当たる環境では、体温調節がうまくいかなくなるため、冷えが慢性化しやすくなります。
陽虚による冷え性—体を温める力が足りない
特徴
✅ 全身が冷える、寒さに弱い
✅ 布団に入ってもなかなか温まらない
✅ 汗をかきやすく、冷えが悪化する
悪循環—発汗→冷えの繰り返し
体の熱を作る力が不足すると、寒さを感じやすくなり、汗をかいた後にさらに冷えてしまう悪循環が起こります。
漢方処方
☑ 桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶとう) → 体を温め、冷えと湿気を改善
☑ 八味地黄丸(はちみじおうがん) → 腎の力を補い、体全体を温める
このタイプの冷え性は、「温める力を補う」ことが大切です。
血虚による冷え性—血の不足で末端が冷える
特徴
✅ 手足の先が冷える、皮膚が乾燥しやすい
✅ 冬になるとしもやけができやすい
✅ 貧血気味で、ふらつきやすい
血の不足が冷えを引き起こす
血が不足すると、末端まで十分な温かさが届かなくなり、手足が特に冷えやすくなります。
冷えによる体へのダメージは少ないのですが、病態がすすむと月経痛や月経不順などのトラブルが出てきます。陽虚と血虚の両方を持っている人も多く、血虚が悪化すると陽虚になりやすくなります。
漢方処方
☑ 当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう) → 血を補いながら体を温める
このタイプの冷え性は、「血を補いながら温める」ことがポイントになります。
気滞による冷え性—精神的なストレスが原因
特徴
✅ 精神的なストレスで手足が冷える
✅ 緊張するとすぐに冷える
✅ リラックスすると温かくなる
冷えの治療はいらない?
気滞による冷え性は、実際には冷えが本質的な問題ではなく、精神的な要因が原因となっています。そのため、温めることよりも気の巡りを整えることが大切です。
緊張しやすく、イライラしがちで、暑がりで薄着なのに手は冷えているといったタイプです。
漢方処方
☑ 四逆散(しぎゃくさん) → 気の流れをスムーズにし、緊張を緩和
このタイプの冷え性は、「気の巡りを改善する」ことを意識しましょう。
水毒による冷え性—体の水分が冷えを引き起こす
特徴
✅ むくみやすく、冷えを感じる
✅ 冷たい飲み物でさらに冷えやすい
✅ 体が重だるい
水毒と冷えの関係
水の巡りが悪くなると、冷えを感じやすくなります。また、陽虚の人は水毒になりやすいため、冷えとむくみの両方を改善することが大切です。
冷えの症状を改善するためにせっせと温めてもなかなか改善しないこのタイプは、むくみをとることで冷えの改善がみられます。
漢方処方
☑ 真武湯(しんぶとう) → 陽を補いながら水の巡りを改善
☑ 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん) → 血を補い、余分な水分を排出
このタイプの冷え性は、「水の巡りを整えながら温める」ことを意識しましょう。
養生・セルフケアのポイント
1. 過ごし方
✅ お風呂はぬるめのお湯でゆっくり入る(熱すぎると逆効果)
✅ 体を締め付ける服を避け、適度な防寒を意識する
✅ 適度な運動を取り入れ、血流を促進する
2. 食べ物
✅ 温める食材(生姜、シナモン、黒糖、ナツメ、羊肉、ネギ、ニラ、ニンニク、唐辛子)を積極的に摂る
✅ 冷たい飲み物を避け、常温または温かいものを選ぶ
✅ 消化の良い食事を心がけ、胃腸をいたわる
次回テーマ:かぜの原因と漢方処方
次回のDrip & Dose Journalでは、「かぜ—東洋医学が示す体質別の治し方」 をテーマにお届けします。
✅ 風邪の種類と漢方的アプローチ
✅ 「寒気がある風邪」と「熱っぽい風邪」、それぞれの対策
✅ 養生法とセルフケア—日常生活でできる風邪予防
気温や体調の変化に敏感な季節、漢方的な風邪の治し方を学びましょう!

【キーワード】
- 「冷え性 漢方」
- 「血虚 冷え性 改善」
- 「水毒 冷え性 原因」
- 「冷え性と生薬」
- 「漢方冷え性タイプ診断」