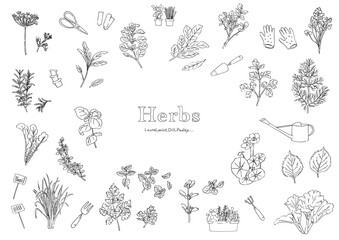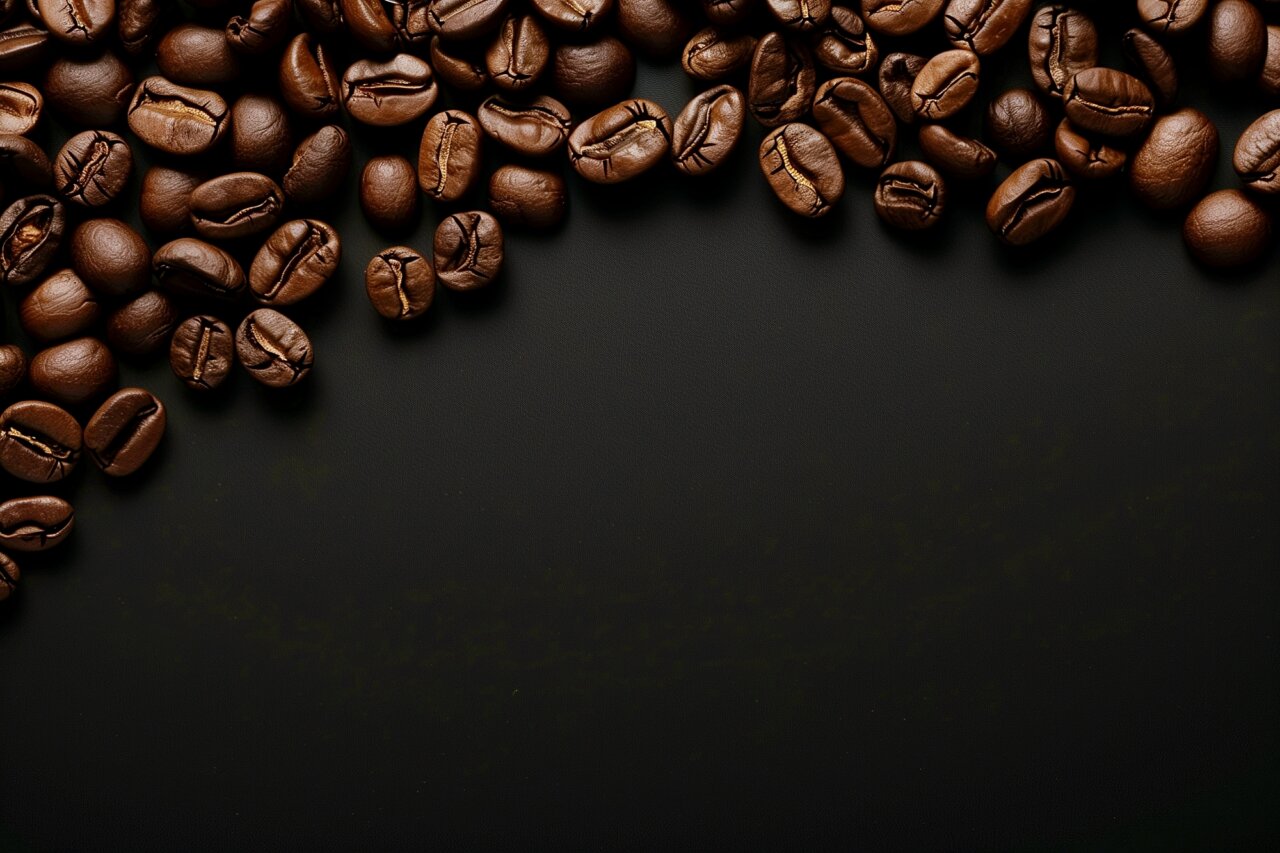こんにちは。Drip & Dose Journal へようこそ!
私は現役薬剤師として、医療の現場で培った知識を活かしながら、コーヒー、漢方、健康、そして生活に関する情報を発信しています。今日は、コーヒーを「漢方的視点」で捉え、健康への影響を深く掘り下げてみたいと思います。
コーヒーは薬か、それとも養生か?
コーヒーと漢方、一見するとまったく異なるものに思えますが、実はコーヒーにも東洋医学的な働きがあるのをご存じでしょうか?
漢方では、「食べるものすべてが薬」と考えられています。この考え方に基づくと、コーヒーもまた生薬の一種として捉えることができます。コーヒーは単なる嗜好品ではなく、適切に摂取すれば体調管理に役立つ「養生食品」となり得るのです。
コーヒーの「気・血・水」への作用
漢方の基本的な考え方である「気・血・水」のバランスに照らし合わせて、コーヒーの働きを見ていきましょう。
気を巡らせる—覚醒と気力の向上
コーヒーに含まれるカフェインは、自律神経を刺激し、脳の覚醒を促します。これは漢方的に見ると「気」を活性化する働きがあります。「気」は生命エネルギーを指し、気の巡りが悪いと倦怠感や無気力に繋がります。適量のコーヒーを摂ることで、気を活性化し、集中力を高めることができるのです。
一方で、過剰摂取は「気の消耗」につながるため、注意が必要です。特に、体質的に気が不足しやすい人(疲れやすい人やストレスが多い人)は、コーヒーの摂取量をコントロールすると良いでしょう。
血の巡りを促進—冷えや血流不良への効果
コーヒーは「温性」の食材に分類されるため、適量の摂取は血流を促し、冷え改善に寄与します。特に「瘀血(おけつ)」と呼ばれる血の巡りが滞った状態には、コーヒーが効果的に働く可能性があります。
また、ポリフェノールが豊富に含まれているため、抗酸化作用によって血管を健康に保つ働きもあります。漢方では、「血が巡ることで健康が維持できる」とされるため、コーヒーは血の流れを良くする一助となるでしょう。
水の代謝を調整—むくみ解消への可能性
コーヒーには利尿作用があるため、「水滞(すいたい)」と呼ばれる水分の滞りを改善する効果があります。これは、むくみが気になる人にとって有益な働きとなります。
ただし、漢方の視点では「水」を過剰に排出すると体に負担がかかるため、過剰な摂取は避けるべきです。特に、もともと「陰虚(いんきょ)」と呼ばれる体質(乾燥しやすい体質)の人は、コーヒーを適度に楽しむことが大切です。
コーヒー×漢方=現代のライフスタイルに活かす
このように、コーヒーは漢方的な観点からも健康維持に役立つ可能性があります。ただし、大事なのは「適量を守ること」。体質に合わせた飲み方を意識することで、コーヒーの恩恵を最大限に活かすことができます。
Drip & Dose Journal では、今後も東洋医学とコーヒーの融合を探りながら、現代の生活に役立つ情報を発信していきます。次回の記事では、「体質別・コーヒーの選び方」をテーマに、陰陽五行説を用いて、あなたに合ったコーヒーの種類を解説していきます。
ぜひ、引き続きお付き合いください!